「ドン・パスクワーレ」を楽しむ
─民衆の気持ちを代弁した物語─ 文:石戸谷 結子
◎「オペラ・ブッファの末尾を飾る傑作」
主人公のドン・パスクワーレは、ドンと付くからにはなかなかの家柄の出身で、お金持ち。ケチだけれどお人良しで、騙されやすい。しかもちょっと好色という憎めない人物だ。医者のマラテスタは、狂言回し役で、頭の回転が早く動きも速いやり手。「フィガロの結婚」や「セビリャの理髪師」のフィガロの親戚のようなキャラクター。そして美人で気が強くしたたかなノリーナは、同じオペラのスザンナやロジーナなどと姉妹のよう。パスクワーレの甥のエルネストは、金も力もない頼りない色男。この4人が繰り広げる楽しくて、ちょっとホロリとさせるドタバタ喜劇が「ドン・パスクワーレ」である。
じつはこれら4人は、イタリアに古くから伝わる民衆劇コンメディア・デラルテのお決まりのキャラクターを受け継いでいる。これは16世紀から18世紀始めにかけて流行した、仮面を付けた即興劇。支配階級の年寄りで金持ちのパンタローネを若い召使のコロンビーナや仲介役のアルレッキーノがさんざんコケにして、からかう物語だ。一方南のナポリでも古くから道化役のプルチネッラが活躍する民衆劇が伝わっており、この2つが結びつき、イタリア各地で即興の民衆劇が人気を博した。こうした文化的な土台の上に、18世紀始めにはナポリでオペラ・ブッファ(喜劇的なオペラ)が生まれ、ペルゴレージ、パイジェッロなどの作曲家が活躍するようになる。
そのコンメディア・デラルテの発祥の地の一つが、北イタリアのベルガモ付近といわれる。ガエタノ・ドニゼッティ(1798~1848)はこのベルガモの出身で、おそらくコンメディア・デラルテを身近かに楽しみながら少年時代を過ごした。彼の代表作には「愛の妙薬」や「連隊の娘」などの傑作オペラ・ブッファがあるが、「愛の妙薬」にも劇中劇として、短い民衆劇が挿入されている。
◎イタリア・オペラの黄金期を築いた作曲家
 ガエタノ・ドニゼッティ ドニゼッティが世に認められ始めた頃、大作曲家として権勢を奮っていたロッシーニ(1792~1868)が、1829年に大作「ウィリアム・テル」を発表したあと、なぜかオペラの筆を折ってしまった。その後継者としてドニゼッティと共に名前が浮かび上がってきたのが、ライヴァルといわれたベッリーニ(1801~1835)だった。この3人が活躍した時代をベルカント・オペラの時代と呼ぶ。ベルカントとは美しい声という意味で、ロッシーニがバロック時代の響きや歌唱が理想だと語ったことから使われるようになった。現在もイタリア伝統の美しい響きの歌唱法をベルカント唱法と呼ぶ。3人のあとに世に出たのが、イタリア・オペラ界最大の巨匠ジュゼッペ・ヴェルディ。ドニゼッティは、ロッシーニとヴェルディの中間に位置し、共にイタリア・オペラの黄金期を築きあげた作曲家である。
ガエタノ・ドニゼッティ ドニゼッティが世に認められ始めた頃、大作曲家として権勢を奮っていたロッシーニ(1792~1868)が、1829年に大作「ウィリアム・テル」を発表したあと、なぜかオペラの筆を折ってしまった。その後継者としてドニゼッティと共に名前が浮かび上がってきたのが、ライヴァルといわれたベッリーニ(1801~1835)だった。この3人が活躍した時代をベルカント・オペラの時代と呼ぶ。ベルカントとは美しい声という意味で、ロッシーニがバロック時代の響きや歌唱が理想だと語ったことから使われるようになった。現在もイタリア伝統の美しい響きの歌唱法をベルカント唱法と呼ぶ。3人のあとに世に出たのが、イタリア・オペラ界最大の巨匠ジュゼッペ・ヴェルディ。ドニゼッティは、ロッシーニとヴェルディの中間に位置し、共にイタリア・オペラの黄金期を築きあげた作曲家である。
ドニゼッティは多作家として知られ、50年の生涯に70曲余りものオペラを作曲している。貧しい家に生まれながらも、有名な作曲家でベルガモの教会付属音楽学校の校長をしていた、シモーネ・マイールに才能を認められて基礎をじっくり学び、ボローニャの音楽院に入って才能を磨いた。24歳のときに初演された「グラナダのゾライデ」が成功して認められた。
作品の中には「ランメルモールのルチア」「アンナ・ボレーナ」「ルクレツィア・ボルジア」など、シリアスな傑作も多い。そんなドニゼッティが最晩年になり、それまでの知識や円熟の作曲技法の全てを投入して作曲したのが、この「ドン・パスクワーレ」だった。台本は幼い頃から親しんだ民衆劇。しかし19世紀にはその流行も陰りを見せており、これがオペラ・ブッファの最後の傑作といわれている。作品は1843年1月3日、パリのイタリア座で初演され、大成功を収めた。
◎「ドン・パスクワーレ」の見どころ聴きどころ
お馴染みのキャラクターが登場し、尊大なお金持ちが最後に召使いや女性たちに痛い目に合わされるという民衆の気持ちを代弁したストーリー。すったもんだの後には、何はともあれハッピーエンドで終わる。これが、オペラ・ブッファのお約束事だ。このお気楽な物語に、ドニゼッティは美しく抒情的でニュアンスに富んだ旋律をたっぷり散りばめた。
 第1幕ではドン・パスクワーレの友人で医者のマラテスタが、花嫁として紹介する自分の妹(じつはノリーナ)の美しさを褒めるアリア、「その美しさは天使のよう」が聴きどころ。若く美しくおしとやかだというので、ドン・パスクワーレは期待に胸ふくらませ、すっかりご機嫌。財産をくれるはずだった叔父のドン・パスクワーレが、若い女性と結婚すると聞き、夢が破れたエルネストは、アリア「ぼくの清らかな夢よ」を切々と歌う。
第1幕ではドン・パスクワーレの友人で医者のマラテスタが、花嫁として紹介する自分の妹(じつはノリーナ)の美しさを褒めるアリア、「その美しさは天使のよう」が聴きどころ。若く美しくおしとやかだというので、ドン・パスクワーレは期待に胸ふくらませ、すっかりご機嫌。財産をくれるはずだった叔父のドン・パスクワーレが、若い女性と結婚すると聞き、夢が破れたエルネストは、アリア「ぼくの清らかな夢よ」を切々と歌う。
一方エルネストの恋人ノリーナは、自宅でくつろぎながら「あの眼差しに、かの騎士は」と恋物語を読みながら、恋愛について想いを馳せる。若い未亡人のノリーナは、なかなかにしたたか。「私は頭もいいし美人だし、男心をつかむ術も知っているわ」と歌う。そこにマラテスタが現れ、ドン・パスクワーレを騙してエルネストと結婚するため、ひと芝居打つことを提案する。ここで、二人の軽快な二重唱「準備は万端よ!」が始まる。
第2幕は、エルネストのアリア「哀れなエルネストよ」から始まる。全幕の聴きどころでもある美しい旋律で、トランペットの伴奏が付く。続いて「遠い地を探しに行こう」と歌い、エルネストは家を出る決心をする。修道院から出てきたばかりの純真な娘に変装したノリーナが、マラテスタに連れられて現れる。それを見たドン・パスクワーレはすっかり気に入り、すぐ結婚しようという。そこに何も知らないエルネストが現れて事態は混乱。結婚書類に署名したとたん、ノリーナが本性を現してわがまま女性に変身。この変身ぶりとドタバタ場面が見どころだ。
第3幕は、手に負えないほどわがままになり、お金を浪費する花嫁にすっかり手を焼いたドン・パスクワーレ。浮気までしている妻の様子に離婚を考える。夜の庭で逢い引きする現場を押さえようと「そっとそっと、今すぐに」とドン・パスクワーレとマラテスタは、早口言葉を駆使して軽快な二重唱を歌う。夜の庭に出たエルネストは、「快い 4月の夜よ」とメランコリックな旋律のセレナーデを歌う。ノリーナと逢い、愛の二重唱が歌われたあと、ドン・パスクワーレが現れる。ここでお芝居の真相が明かされ、パスクワーレは甥とノリーナの結婚を認め、大団円で終わる。
さてこの物語、最後に「教訓(オチ)」が付いている。「老人が結婚を望むのは愚かなこと」と、ノリーナは楽しく歌うのだが、さて皆様、この教訓をどうお考えでしょう?
石戸谷 結子
音楽ジャーナリスト
青森県生まれ。早稲田大学卒業。音楽之友社を経て、1986年からフリーランスの音楽ジャーナリストに。『音楽の友』『モストリー・クラシック』『東京新聞』などに執筆。おもな著書『マエストロに乾杯』(光文社)、『石戸谷結子のおしゃべりオペラ』(新書館)、『ひとりでも行けるオペラ極楽ツアー』(朝日新聞出版)など。
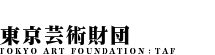

 フォトギャラリー
フォトギャラリー